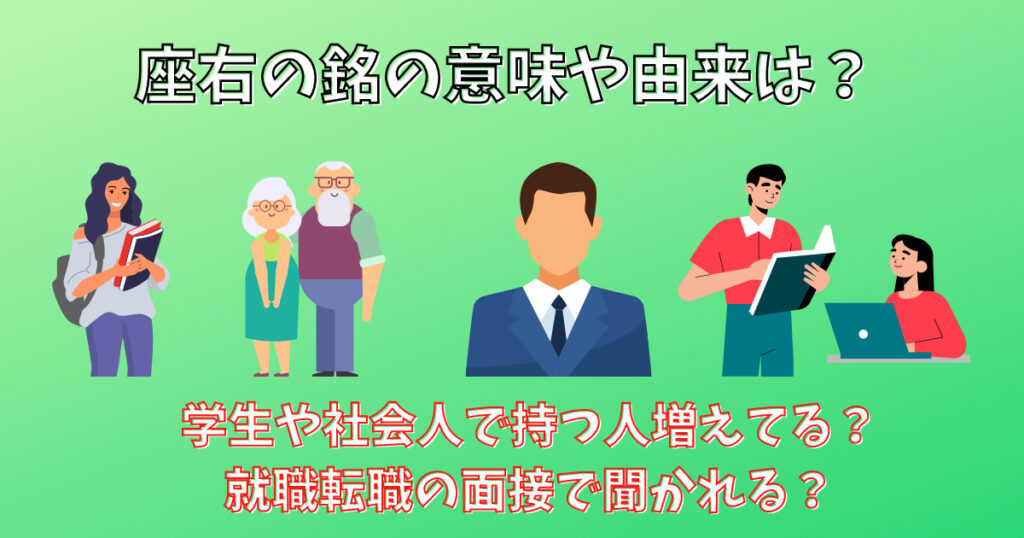メジャーリーグで活躍中の大谷翔平選手の「座右の銘」は、「先入観は可能を不可能にする。」だそうです。「おぉ~、すごい人はそんな風に考えてがんばってきたのかあ!」と、感心してしまいますよね。
「座右の銘」は、「すごい人の持っているポリシーのようなもの。」という漠然としたイメージがありますが、本来の意味はどういったものなのでしょうか?最近では就職の面接などでも聞かれることがあり、有名人だけでなく、誰でも持つことのできる言葉になっています。

では、今回は「座右の銘」という言葉について、深く調べてみましょう!
目次
座右の銘ってどういう意味?
多くの人が、今までに一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか?「座右」という言葉は、「座っているところのかたわらや、身近」のことを意味します。そして「銘」は、漢字のつくりでもわかるように、金属や石などに刻むことを意味します。
つまり「座右の銘」は、「いつも自分のそばにおいて戒め励まし、迷った時の道しるべとする言葉」という意味です。
この「座右の銘」には、特にルールがありません。四字熟語からことわざ、偉人や恩師が言った言葉、漢字一文字、ただ単に「ありがとう」など、どんなスタイルでもいいですし、いくつ持っていてもかまいません。

多くの人は、仕事で踏ん張らないといけない時や、人生の分岐点、元気がない時、迷った時などに思い出して、心を奮い立たせているようですね。
ちなみに「四字熟語の人気座右の銘」や「年代別の人気おすすめ座右の銘」、「有名人・偉人・アニメで人気の座右の銘」については別記事で紹介しているのでよかったら合わせてご覧ください。
座右の銘の由来は?
由来は中国?皇帝が一番信頼する人間を配置する場所が右側?
「座右の銘」の由来は、古く中国にさかのぼります。皇帝などの地位の高い人は、自分が尊敬・崇拝する人の言葉を何かに刻み、そばに置いて過ごしていたと言います。
皇帝などになれば、ひとつひとつの決断も大きく、迷いがあるでしょう。その時にその言葉を見て、選ぶべき道を冷静に判断していたのです。
その言葉が置かれていたのが、そう「右側」なのです。
右は、皇帝が一番信頼する人間を配置する場所。そのぐらい、その言葉を大切に、頼りにして過ごしていたことがわかりますね。

一番古い座右の銘は、後漢のさいえんという詩人が記録した、「座右銘」と言われています。日本では空海が書写したものが有名ですよ。
「座右の銘」を持つ人は高齢者だけでなく学生や若い社会人も増えている?
ある調査では、なんと56%が「持っている」と答えています。
2人に1人は持っているとは驚きです。世代別にみると、一番多いのは60代。やはり人生で多くのことを乗り越えてきた世代が、学んだことを心に刻んでいるのかもしれません。
学生や若い世代でも座右の銘を持つ人が増えている?
「現代の若い人は、迷うことが多いのかな?」と思いきや、引用は憧れの人やアニメの登場人物なども多く、中学生、高校生の夢や目標に向かう原動力となっているようです。
また、大学生は就職の面接や履歴書の自己PR欄などで、書く必要に迫られます。社会人になれば、転職や自己紹介をする時に、さりげなく「座右の銘」を付け加えると印象に残るので、準備しておくと良いでしょう。

現代では、自己アピールのひとつとして、活用されているのですね。
「座右の銘」は就職転職の面接でも聞かれる?
それでも最近は、就職や転職の面接の場で、「座右の銘」を聞かれることがあるようです。
これは、その就活生がどんな性格や価値観、行動特性を持っているのかを知るための質問のようです。それを聞いて、「会社の雰囲気とあっているかな?」と判断しているのですね。
学生側からしてみれば、その言葉選びによって、自分の働き方を先方に伝えることができるとも考えられます。
「継続は力なり」なら、努力家と思われるでしょう。「一期一会」なら協調性のアピールになります。

いざ聞かれた時のために、自分に合った言葉を見つけておくと良いでしょう。
まとめ
「座右の銘」と聞くと、なんだか固いイメージで、すごいことを成し遂げた偉人が持つものと思ってしまいがちですが、現代では全くそんな印象はなく、若い人からシニア層まで、気軽に自分の心の言葉を見つけて大切にしているようです。
最近では、自己PRの手段としても使われ、新しい形で広まっていますね。
「座右の銘」のジャンルは幅広いので、立派なフレーズを知らなくとも、自分らしい言葉を選ぶことができるでしょう。
まだ持っていない人は、なんだかピンと来る言葉に注目してみてください。それがあなたの人生を助ける「座右の銘」になるかもしれませんよ。