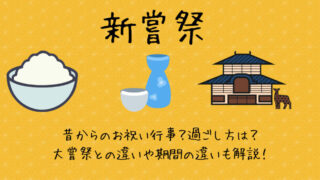 文化
文化 新嘗祭は昔からのお祝い行事?過ごし方は?大嘗祭との違いや期間の違いも解説!
新嘗祭とは、11月23日(もと陰暦十一月の中の卯(う)の日)に毎年行われ、宮中三殿の近くにある神嘉殿で行われる宮中行事です。新嘗祭は古事記にも記されている?お祝い行事?新嘗祭の「新」は新穀、「嘗」は御馳走を表しています。現在は11月23日は...
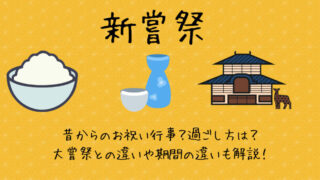 文化
文化 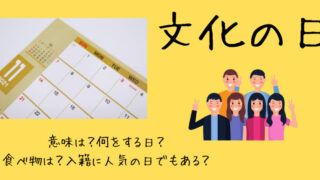 暦
暦 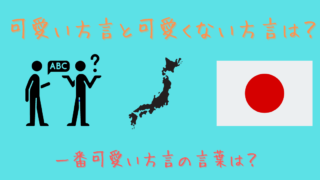 文化
文化  文化
文化  3月
3月  季節
季節  5月
5月  3月
3月  文化
文化  3月
3月