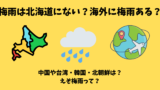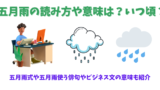しかし春と夏の間にある梅雨(つゆ)は、長雨が続きうっとうしく感じる期間ですね。
梅雨はいつからいつまでなのか?平均はいつ頃なのか?

私たちになじみのある梅雨(つゆ)について、おさらいしてみましょう。
目次
2024年の梅雨入りと梅雨明けはいつ頃?【沖縄・九州・四国・近畿・関東甲信・東北・北海道】
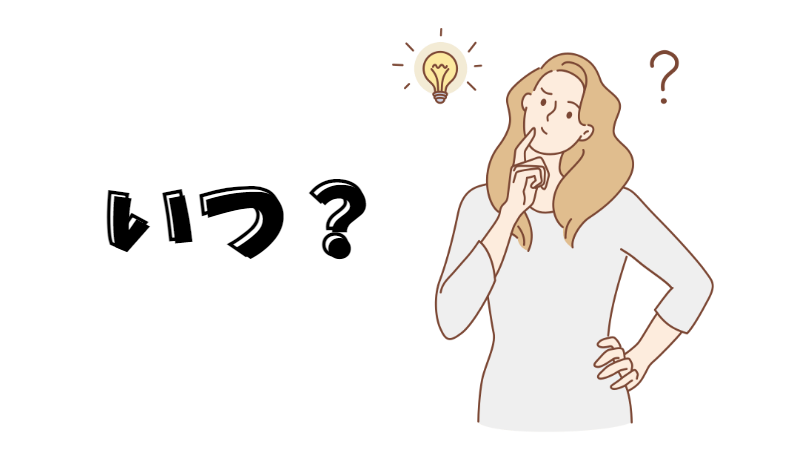
2024年の梅雨入りは?【沖縄・九州・四国・近畿・関東甲信・東北・北海道】
| 地方 | 2024年(令和6年) | 平年 | 昨年 |
|---|---|---|---|
| 沖縄 | 5月21日ごろ | 5月10日ごろ | 5月4日ごろ |
| 奄美 | 5月21日ごろ | 5月12日ごろ | 5月5日ごろ |
| 九州南部 | 6月8日ごろ | 5月30日ごろ | 6月10日ごろ |
| 九州北部 | 6月17日ごろ | 6月4日ごろ | 6月11日ごろ |
| 四国 | 6月9日ごろ | 6月5日ごろ | 6月11日ごろ |
| 中国 | 6月22日ごろ | 6月6日ごろ | 6月11日ごろ |
| 近畿 | 6月21日ごろ | 6月6日ごろ | 6月14日ごろ |
| 東海 | 6月21日ごろ | 6月6日ごろ | 6月14日ごろ |
| 関東甲信 | 6月21日ごろ | 6月7日ごろ | 6月6日ごろ |
| 北陸 | 6月22日ごろ | 6月11日ごろ | 6月6日ごろ |
| 東北南部 | 6月23日ごろ | 6月12日ごろ | 6月6日ごろ |
| 東北北部 | 6月23日ごろ | 6月15日ごろ | 6月6日ごろ |
2024年の梅雨明けは?【沖縄・九州・四国・近畿・関東甲信・東北・北海道】
| 地方 | 2024年(令和6年) | 平年 | 昨年 |
|---|---|---|---|
| 沖縄 | 6月20日ごろ | 6月21日ごろ | 6月20日ごろ |
| 奄美 | 6月20日ごろ | 6月29日ごろ | 6月22日ごろ |
| 九州南部 | 7月17日ごろ | 7月15日ごろ | 7月22日ごろ |
| 九州北部 | 7月22日ごろ | 7月19日ごろ | 7月22日ごろ |
| 四国 | 7月19日ごろ | 7月17日ごろ | 7月22日ごろ |
| 中国 | 7月21日ごろ | 7月19日ごろ | 7月26日ごろ |
| 近畿 | 7月21日ごろ | 7月19日ごろ | 7月23日ごろ |
| 東海 | 7月18日ごろ | 7月19日ごろ | 7月23日ごろ |
| 関東甲信 | 7月18日ごろ | 7月19日ごろ | 7月23日ごろ |
| 北陸 | 8月1日ごろ | 7月23日ごろ | – |
| 東北南部 | 8月1日ごろ | 7月24日ごろ | – |
| 東北北部 | 8月2日ごろ | 7月28日ごろ | – |
全国の梅雨入りと梅雨明けは例年・平均はいつ頃?【沖縄・九州・四国・近畿・関東甲信・東北・北海道】


以下では沖縄から東北(沖縄・九州・四国・近畿・関東甲信・東北・北海道)までの梅雨入りと梅雨明けがいつ頃なのかを紹介します。
沖縄の梅雨入りと梅雨明けはいつ頃?【いつからいつまで】

過去の気象庁のデータを見てみると、最も早い梅雨入りは1980年の4月20日頃、最も遅い梅雨明けは2019年7月10日頃になっています。
九州地方の梅雨入りと梅雨明けはいつ頃?【いつからいつまで】
しかし、気象庁のデータを見ると、九州地方は南部と北部では梅雨入り、梅雨明けの時期にずれがあります。

また九州地方北部の平均的な梅雨入りは6月4日頃、梅雨明けは7月19日頃とされています。九州地方でも南部と北部ではそれぞれ5日ほどのずれがあります。
四国地方の梅雨入りと梅雨明けはいつ頃?【いつからいつまで】

過去の気象庁のデータを見てみると、最も早い梅雨入りは2021年の5月12日頃、最も遅い梅雨明けは1954年の8月2日頃になっています。
近畿地方の梅雨入りと梅雨明けはいつ頃?【いつからいつまで】

しかし過去の気象庁のデータを見てみると、最も早い梅雨入りは1956年と2011年の5月22日頃、最も遅い梅雨明けは2009年の8月3日頃になっています。
関東甲信地方の梅雨入りと梅雨明けはいつ頃?【いつからいつまで】

しかし過去の気象庁のデータを見てみると、最も早い梅雨入りは1963年の5月6日頃、最も遅い梅雨明けは1982年の8月4日頃になっています。
東北地方の梅雨入りと梅雨明けはいつ頃?【いつからいつまで】
しかし、気象庁のデータを見ると、東北地方の南部と北部では梅雨入り、梅雨明けの時期にずれがあります。

東北地方北部の平均的な梅雨入りは6月15日頃、梅雨明けは7月28日頃とされています。東北地方でも南部と北部では3日ほどのずれが生じています。
北海道の梅雨入りと梅雨明けはいつ頃?【いつからいつまで】
北海道って梅雨ないの?って人は別記事で紹介しているので合わせてご覧ください。
まとめ
毎年やってくる梅雨は正直うっとうしい時期ですが、日本で暮らす私たちにとって適度な雨量の梅雨は欠かせないものです。
梅雨入りの発表は日常生活を送るうえで気になるものですが、気象を専門にしている気象庁でも梅雨入りの判断が難しいのです。
梅雨は自然がもたらす気象現象だけに、昨今の地球温暖化による影響もとても気になります。長雨が続きますが「災難の雨」ではなく「恵みの雨」であることを願うばかりです。
ちなみにこの梅雨は江戸時代以前は「五月雨(さみだれ)」と呼ばれていました。「五月雨」については別記事でも紹介しているので興味があれば合わせてご覧ください。