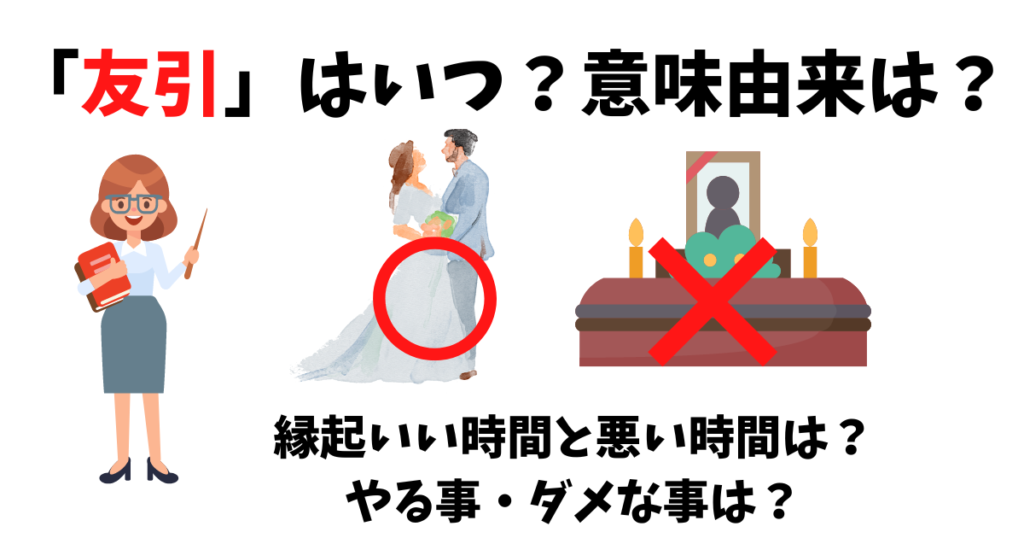さて、この大安や友引は「六曜(ろくよう)」という暦上の占いのひとつで、それぞれに吉凶などの意味があります。大安は有名なのでご存じの方も多いと思いますが、では友引はいかがでしょうか?
なんとなく知っているけど、本来どんな意味があるのか?吉日と言えるのか?まで、ご存じの方は少ないかもしれません。

今回は六曜のひとつ「友引」について、意味や由来、いつなのか?なぜ「お葬式はするな」と言われるのかまで、調べてみたいと思います。
目次
「友引」の意味由来は?読み方は?
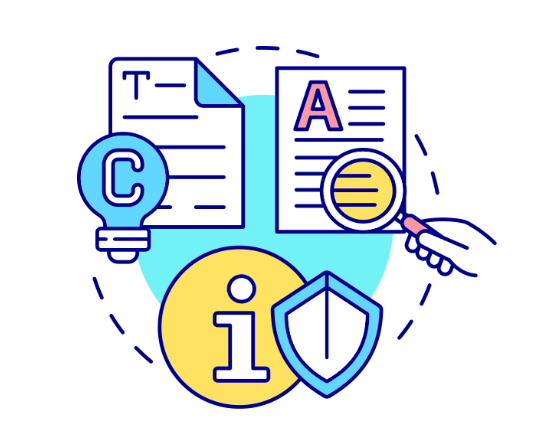
「友を引き寄せる」という意味のイメージが強いですが、初めからそうだったわけではないようです。
本来六曜は古く中国で生まれた占いで、その後、鎌倉・室町時代に日本に渡り、江戸時代に庶民に広まったと言われています。
三国志で有名な諸葛孔明が考えた
その由来には諸説あり、大元となる考え方は、三国志で有名な諸葛孔明(しょかつこうめい)が戦のために考えたものとも言われています。
そのため、もともとは「争いごとがともに引き分ける・勝負がつかない日」という意味を持っており、「共引」と表記されていたこともあります。
陰陽道を踏まえて日本に伝わり意味が変わっていった
後に陰陽道(おんみょうどう)を踏まえて日本に伝わり、現在では友引と書き、友を引きこむという意味を持つようになったのです。
「友引」はいつ?2024年の日程は?
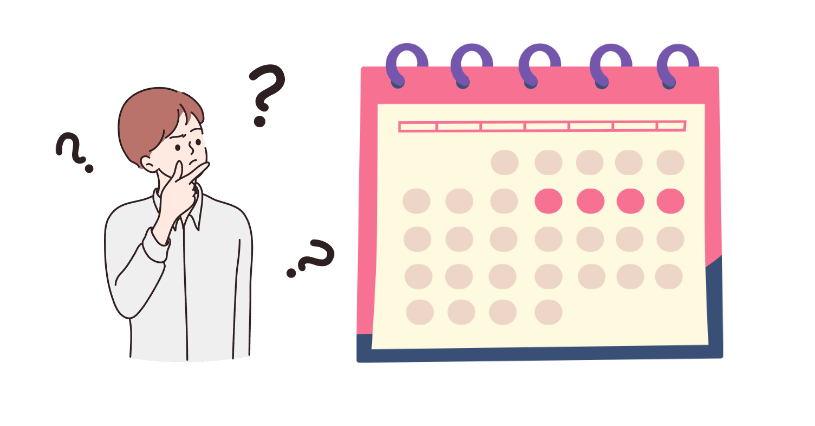
ですが、時々同じ六曜が続いたり、ずれこんでしまう日があります。
これは、月によって1日の六曜が決まっているからなのです。たとえば「2月1日は友引から、5月1日は大安から」といった感じです。ここで言う月とは、旧暦の月のことなので、現代のカレンダーで表記すると、少しずれてしまうというわけなのです。

ちなみに、友引から始まるのは、2月と8月です。
2024年の友引はいつ?日程紹介
- 1 2024/1/3 水
- 2 2024/1/9 火
- 3 2024/1/13 土
- 4 2024/1/19 金
- 5 2024/1/25 木
- 6 2024/1/31 水
- 7 2024/2/6 火
- 8 2024/2/11 日
- 9 2024/2/17 土
- 10 2024/2/23 金
- 11 2024/2/29 木
- 12 2024/3/6 水
- 13 2024/3/10 日
- 14 2024/3/16 土
- 15 2024/3/22 金
- 16 2024/3/28 木
- 17 2024/4/3 水
- 18 2024/4/14 日
- 19 2024/4/20 土
- 20 2024/4/26 金
- 21 2024/5/2 木
- 22 2024/5/12 日
- 23 2024/5/18 土
- 24 2024/5/24 金
- 25 2024/5/30 木
- 26 2024/6/5 水
- 27 2024/6/9 日
- 28 2024/6/15 土
- 29 2024/6/21 金
- 30 2024/6/27 木
- 31 2024/7/3 水
- 32 2024/7/8 月
- 33 2024/7/14 日
- 34 2024/7/20 土
- 35 2024/7/26 金
- 36 2024/8/1 木
- 37 2024/8/5 月
- 38 2024/8/11 日
- 39 2024/8/17 土
- 40 2024/8/23 金
- 41 2024/8/29 木
- 42 2024/9/3 火
- 43 2024/9/9 月
- 44 2024/9/15 日
- 45 2024/9/21 土
- 46 2024/9/27 金
- 47 2024/10/8 火
- 48 2024/10/14 月
- 49 2024/10/20 日
- 50 2024/10/26 土
- 51 2024/11/5 火
- 52 2024/11/11 月
- 53 2024/11/17 日
- 54 2024/11/23 土
- 55 2024/11/29 金
- 56 2024/12/4 水
- 57 2024/12/10 火
- 58 2024/12/16 月
- 59 2024/12/22 日
- 60 2024/12/28 土
以上となります。

六曜は定期的にめぐって来るので、お祝いごとのスケジュールも組みやすいですね。
「友引」の縁起のいい時間は?悪い時間は?何時から何時まで?

六曜は、陽が昇って沈むまでを3つ、陽が沈んで昇るまでを3つの、合計6つの時間帯に1日を分けて吉凶をつけます。「先勝ならば午前が吉運で午後が凶運」といった感じです。
何時から何時まで?朝と晩は吉運?11~13時は凶運?
友引は、朝と晩は吉運です。そして、一日の真ん中、午(うま)の刻だけが凶運の日と言われています。午の刻は、具体的には11~13時の間になります。

友引でも凶運時間が気になる方は、結婚式を正午にスタートするなどは避けた方が賢明でしょう。
「友引」過ごし方や向いている事は?葬式や通夜は?結婚式・入籍や納車は?

結婚式・入籍は最適?引っ越しも最適?
友引は吉日なので、縁起の良い行事にはとても向いています。中でも結婚式・入籍は最適。「友を引く」という意味から、友達を幸せに巻き込んでくれると言われています。
新しい生活の始まる引っ越しも、吉日に行うことが多い行事なので向いています。
ですが、三隣亡(さんりんぼう・土地にまつわる行事をすると、その後、三軒となりまで火事になると言われる凶日)と重なると、友引の効果は負けてしまうので注意しましょう。
「三隣亡(さんりんぼう)」についてもっと知りたい!って人は別記事でも紹介しているのでよかったら合わせてご覧ください。
納車は?
吉日を選びがちな納車も、友引に向いていますが、人によっては「友を轢く」と考えてしまい、納車を避ける人もいるようです。
お参りや法事は?
六曜は基本的に神道や仏教とは関係がないため、神道に由来するお参りや、仏教に由来する法事は問題がないと言われています。
お葬式はしないほうがよい?お通夜は?
お葬式だけは「友を道連れにする」という意味から、絶対にNGです。
仏教とは関係がないのですが、参加する方などに信じている人も多いため、配慮するという意味で避けた方が良いでしょう。

お通夜はお葬式ほどNGではありませんが、その後のお葬式の日程を優先して考えると良いでしょう。
まとめ
いかがでしたか?六曜の吉日・友引がどんな日か、おわかりいただけたでしょうか?
多くの人に知られている「友達を呼び込む日」という意味以外に、お昼の時間帯は少し運気が下がるという、注意するべき一面もありました。
現代では、科学的根拠のない暦の占いを、迷信だとして気にしない人も多いと思います。確かに友引に結婚したからと言って、絶対に離婚しないというわけではありませんよね。ですが、人生の大一番という日は誰でも不安です。少しでも自信を持って立ち向かいたいという健気な思いから、多くの人が暦に頼ってしまうのだと思います。
江戸時代には、人々が暦に頼りすぎて禁止令が出たこともあるほど。今も昔も、暦は不安な人々の心を支えてくれるためにあるのかもしれませんね。