ここでは「立夏」について詳しく紹介していきます。
夏と言う字がありますが、現在の暦に当てはめるとまだ本格的な夏の時期ではないんですよ。

立夏はいつなのか?意味由来、七十二候などを見ていきましょう!
立夏の意味・由来は?暦便覧での意味は?
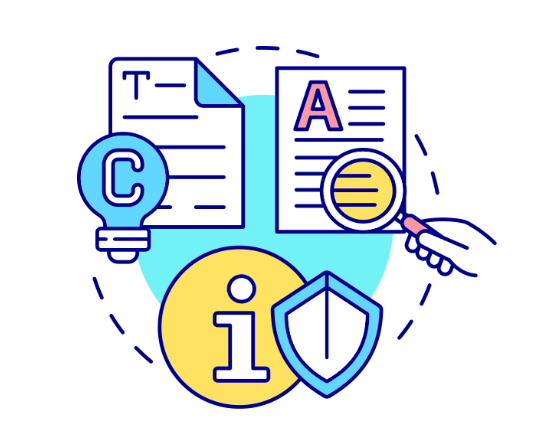
立夏は春分と夏至のちょうど真ん中で、暦の上での夏の始まりとなります。意味由来としては漢字の通り夏が立つから分かるように「夏の始まり」を意味すると言われています。立夏から立秋の前日までが暦では夏季になります。
天文学的には、太陽が黄経45度の点を通過する時のことをいいます。
まだ季節としてはそこまで夏の暑さを感じない時期ではありますが、山にも青葉が目立ち始め、明るく強い日差しもあいまって夏の気配を感じ始める頃です。

時には汗ばむくらい気温が上がることもありますよね!
書物【暦便覧】による立夏の意味は?
江戸時代にこよみを記した書物【暦便覧】によると、立夏は「夏の立つがゆへ也」と記されており、これは夏らしい気配があらわれてくることを意味しており、「夏がはじまりますよ!」という合図の意味です。

立夏は「夏立つ」「夏来る」などとともいわれ、夏の代表的な季語にもなっています。
立夏はいつ?日付は?2024年はいつ?
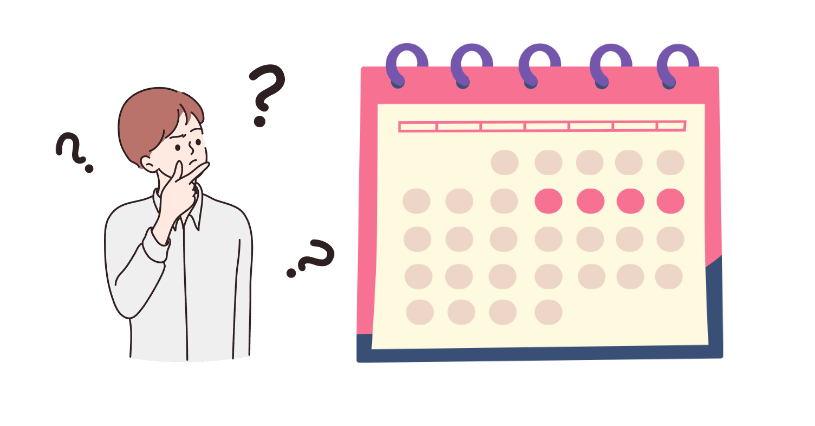
2024年の立夏はいつ?
2024年の立夏は5月5日日曜日です。

ゴールデンウイーク時期で過ごしやすい頃、暑さに対する備えをしつつも夏とはまだ到底思えない心地よいこの季節を楽しみましょう
立夏の七十二候は?

15日を5日ずつの期間に分けて、それぞれ「初候(しょこう)・次候(じこう)・末候(まっこう)」と呼びます。
立夏の七十二候は以下の通りです。
| 初候 | 蛙始鳴(かわずはじめてなく) | 蛙が鳴き始める |
|---|---|---|
| 次候 | 蚯蚓出(みみずいづる) | 蚯蚓(みみず)が地上に這出る |
| 末候 | 竹笋生(たけのこしょうず) | 筍(たけのこ)が生えて来る |
青葉が生い茂る中に日差しがこもれ、土の上ではカエルやミミズなどが活発に活動しはじめている。まるで初夏の様子をが目にうかんできますね。
まとめ
立夏はいつなのか?意味由来や、七十二候なども分かりましたでしょうか。
「暦の上では夏となりました」なんてフレーズを耳にするかもしれません。5月5日頃から20日頃ですから、まだ夏というよりも初夏です。
ですがあっという間に暑い時期はやってきます。エアコンのお掃除をするなど暑さ対策を考え始めてみてはいかがでしょう。
季語として、時候の挨拶などでも用いられる立夏、どうやら最近はお子さんの名前として使われることも増えているようです。いつの時期に生まれたか名前で分かりますね。


