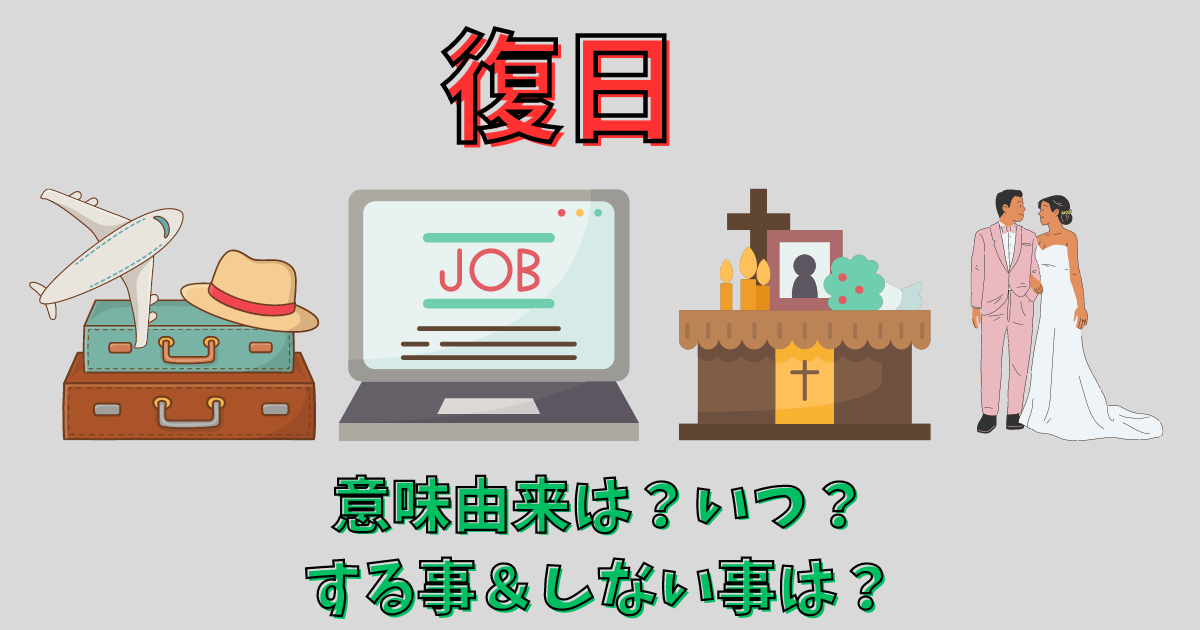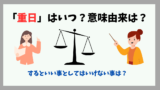そこまで縁起や占いを気にしていなかったとしても、「結婚式は大安の日に。」と、思わず運を気にしてしまうこともありますね。
ですが、いくら縁起を担いでも、結局は自分の行動で結果が出るもの。暦の中には、そんな自分のした行動の運気をアップしてくれる日というものがあるのをご存じでしょうか?
暦の占い、「歴注下段(れきちゅうげだん)」のひとつに、「復日」があります。この日は、暦自体には良い悪いが決まっていないのですが、この日に行ったことの運気を上げてくれるという性質があるのです。

とてもめずらしい暦なので、ぜひ、チェックしてみてくださいね!
目次
「復日」の意味由来は?
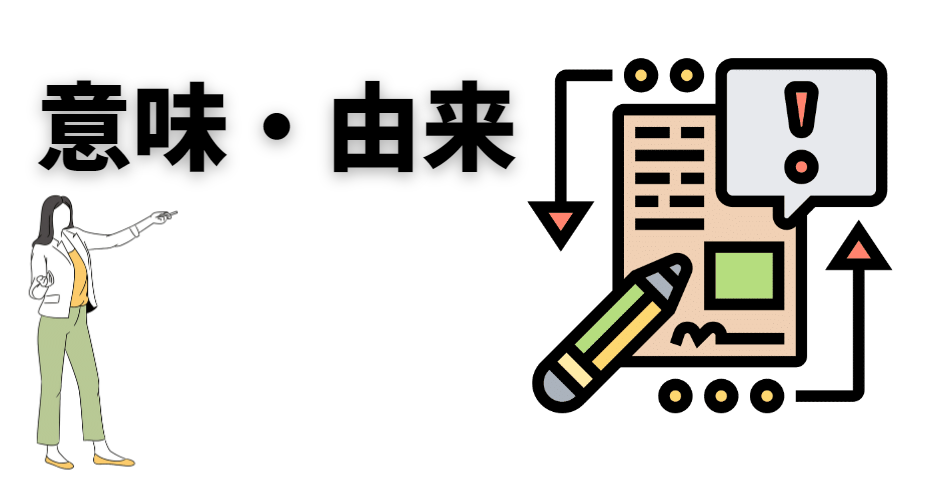
意味は?
漢字のイメージ通り、この日は「吉事をすれば吉運が重なり、凶事をすれば凶運が重なる。」という意味の暦です。
つまり、良い運気のことはどんどん縁起が良くなり、反対に悪い運気のことをするとどんどん縁起が悪くなるという、歴注下段の中でもめずらしい暦なのです。
暦は、ほとんどのものが吉日、凶日と分けられますが、「復日」に関してはそのどちらでもなく、自分の行動次第で吉にも凶にできる日なのです。
由来は?
由来はハッキリしていないのですが、陰陽五行説(いんようごぎょうせつ)をもとにして作られたのではないかと言われています。
陰陽五行説では、全てのものが「木、火、水、土、金」の5つの性質に分類されます。存在するものだけでなく、年、月、日などにも、この性質が割り当てられます。
その内、月と日で、同じ性質が重なる日のことを「復日」としたようです。

復日の考え方は、927年に書かれた延喜式にも記載があり、歴史は長い言葉と言われています。
「復日」はいつ?2024年は?
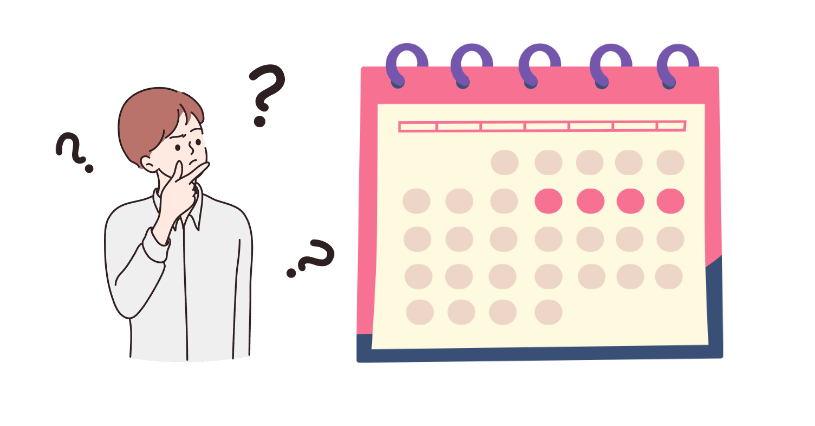
「二十四節気」は、立春、夏至などの季節の変わり目で月の区切りを表します。十干は、12日で1サイクルの干支と違って、「甲乙丙丁戌己庚辛壬癸」の10種類の言葉を当てて毎日を表し、10日間で1サイクルとする、中国に由来する考え方です。

この月と十干の、五行の性質が重なる日を復日としています。
各月の「復日」
- 1、7月…甲(きのえ)と庚(かのえ)の日
- 2、8月…乙(きのと)と辛(かのと)の日
- 3、6、9、12月…戊(つちのえ)と己(つちのと)の日
- 4、10月…丙(ひのえ)と壬(みずのえ)の日
- 5、11月…丁(ひのと)と癸(みずのと)の日
ここでいう月は、二十四節気の区切り、節切り(せつぎり)をもとに考えられており、現代のカレンダーの月とは少しずれています。
2024年の「復日」
1月4日
1月6日
1月15日
1月16日
1月25日
1月26日
2月6日
2月10日
2月16日
2月20日
2月26日
3月1日
3月8日
3月12日
3月18日
3月22日
3月28日
4月1日
4月4日
4月5日
4月14日
4月15日
4月24日
4月25日
5月4日
5月8日
5月12日
5月18日
5月22日
5月28日
6月1日
6月8日
6月12日
6月18日
6月22日
6月28日
7月2日
7月13日
7月14日
7月23日
7月24日
8月2日
8月3日
8月8日
8月14日
8月18日
8月24日
8月28日
9月3日
9月8日
9月14日
9月18日
9月24日
9月28日
10月4日
10月11日
10月12日
10月21日
10月22日
10月31日
11月1日
11月8日
11月14日
11月18日
11月24日
11月28日
12月4日
12月9日
12月15日
12月19日
12月25日
12月29日

1年間でかなりたくさんある事が分かりますね!
「復日」にするといい事としてはいけない事は?【契約・引っ越し・結婚は?】

契約・旅行はするといい?
行動の運気が増してゆく復日は、もちろん吉事に向いており、特に善い行いをすると、さらに運気がアップすると言われています。
吉運が増してゆくので、お金を貸すなどの契約や、旅行などにも向いています。
結婚・入籍・葬式・就職・引越しはしないほうがいい?
「復日」は「何度も繰り返してはまずい。」と思われるイベントは不向きです。
中でも結婚式は、再婚を連想するので特に避けられます。また、お葬式関連や就職、引っ越しなども、できれば控えた方が良いでしょう。

とはいえ、暦注下段という占いは科学的根拠がなく、「迷信だ。」とする人も多いものです。あなたが気にならないのであれば、あまり振り回されすぎることはないでしょう。
「復日」と「重日」との違いは?

こちらも、復日と同じように「吉事を行えば吉運が増し、凶事を行えば凶運が増す。」という意味があります。一般的に、この2つは「ほぼ同じ」と考えて良いです。
由来が違いますが、ともに「重なる」という意味があるので、結婚や葬儀に向きません。ですが、重日には、「新しいことを始める、挑戦するのに吉。」というニュアンスがあり、その点は復日とは少し違うと言えるでしょう。
「重日」については別記事で紹介していますのでよかったらあわせてご覧ください。
まとめ
いかがでしたか?暦注下段のひとつ、「復日」がどんな日か、おわかりいただけましたか?
暦自体に運気は決まっておらず、自分の行動次第で吉にも凶にもできる、めずらしい日でしたね。暦注下段には、同じような意味の重日という日があります。重日は年間で約60日ありますので、復日と合わせると3日に1度はこの日がめぐってくることになります。
暦注下段は迷信のようなものではあるので、こだわりすぎる必要はありません。ですが、良い事のために取り入れれば、「ほぼ毎日、運気をアップできる日だ!」と感じられて、楽しいですよね!