俳句の季語などでは使われているものの、日常生活ではほとんど聞かない馴染みのない言葉かと思います。

大雪とはいつのことで、どんな意味をあらわす言葉なのでしょうか。今回は、大雪の意味・期間・暦の考え方などもあわせて、わかりやすく解説していきたいと思います。
目次
暦の大雪って!?
これ、「おおゆき」ではなく「たいせつ」と読むのです。読んで字のごとし、たくさんの雪が降る時期を表す言葉です。
大きなカレンダーであれば書かれてあることもあるでしょう。その昔は、農業を皆がやっていたので気候の変化を知っていることは大変に重要でした。今も、急に寒くなったり朝と晩で温度が全然違ったりといった時期は風邪をひきやすくなります。
大雪という文字を見て、寒さ対策を万全にするように気を付けるとよいでしょう。さまざまな気候が見られる日本、春夏秋冬と4つに分けるのもですが、24個の等分も乱暴と言えるかもしれません。それなら更に細かく分けた、七十二候というものもあります。
大雪とはいつ?2025年は?
ただし、太陽の位置で毎年計算されて日時が決まるため、年によっては8日になることもあります。

二十四節気の1つなので、太陽と地球の位置で決まる為、年によっては日付が違う事もあるのです。
2025年の大雪はいつ?

年によって8日の日もあるのですがだいたいは7日になります!
大雪って何?旧暦の1つ?二十四節気の1つ?

「大雪の言葉自体の意味ってなんなんだろう?」という疑問が残りますよね。

そもそも大雪がなんなのか、どんな意味なのかを詳しくみてみましょう。
大雪とは旧暦の名称?二十四節気の1つ?
大雪とは、二十四節気(にじゅうしせっき)と呼ばれる暦の季節の名称のひとつです。
毎年12月7日頃の旧暦を大雪と呼び、この日から旧暦の冬がはじまります。
大雪の期間は?1日だけではない?
大雪も1日だけでなく、期間としての意味もあります。
大雪の最も多い日付である12月7日を例にすると大雪の期間は12月7日から冬至(とうじ)の前日の12月21日までの15日間になります。
大雪の前は「小雪(しょうせつ)」、小雪があけて大雪をすぎると、12月22日からは「冬至(とうじ)」の季節がはじまります。
大雪の意味・季節は?
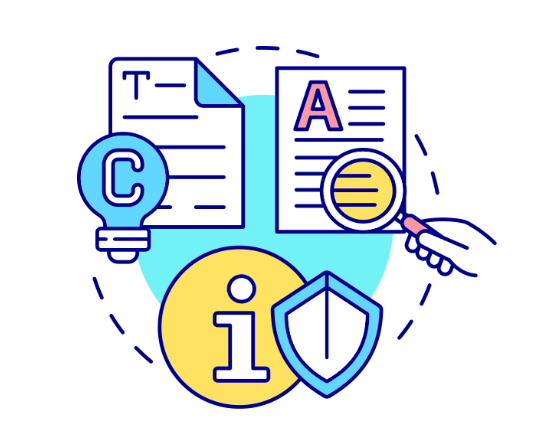
木枯らしが吹き荒れ、雪がたくさんふりはじめる季節です。特に日本海側では激しくふりはじめ、山もすっかり雪景色一色となっていきます。
江戸時代の暦便覧による大雪の説明
大雪は、江戸時代にこよみを記した書物【暦便覧(れきびんらん)】に「雪いよいよ降り重ねる折からなれば也」と記され、いよいよ雪が降ってつもっていく時期と説明されています。
挨拶文で使う「大雪の候」はいつからいつまで?
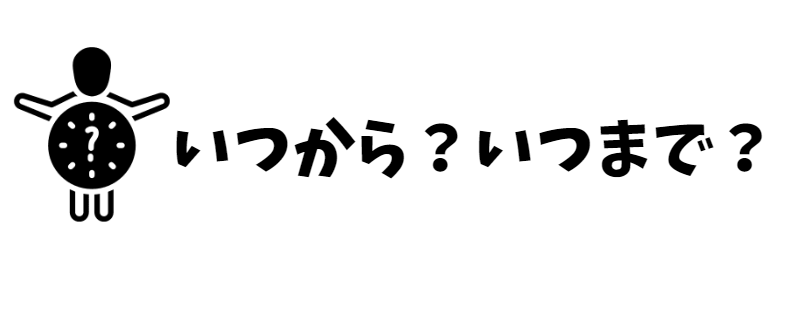
大雪が12月7日の場合は12月7日から12月21日までになります。
大雪の候(読み方:たいせつのこう)とは、冬のはじまりに使われる時候の挨拶です。「雪が積もる季節になりましたが」という意味です。

ただ、昔の気候と今の気候の時期は若干ズレがあります。雪が積もる、にまだふさわしくないと思った場合は「師走(しわす)の候」などを代わりに使うとよいでしょう。
大雪の七十二候の名称と意味
大雪の15日間のうち5日間ずつ、それぞれの期間に分けた七十二候。
それぞれに名前と意味がついています。
| 候 | 名称 | 意味 |
|---|---|---|
| 初候 | 閉塞成冬(そらさむくふゆとなる) | 天地の気が塞がって冬となる |
| 次候 | 熊蟄穴(くまあなにこもる) | 熊が冬眠のために穴に隠れる |
| 末候 | 鱖魚群(さけのうおむらがる) | 鮭が群がり川を上る |
熊が冬眠したり、鮭が産卵のために川を上っていくなど、冬の代名詞といえるような情景がそれぞれ描かれているんですね。
まとめ
大雪について、読み方・意味・期間などは理解できたでしょうか。背景には二十四節気・七十二候という旧暦の考え方があったんですね。日本の文化は本当にどこまでも奥深いです。
冬があけたら春はすぐそこ。春を待ち遠しく過ごすのは、昔も今も変わらないのかもしれませんね。

