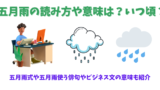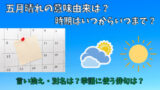ですがその昔、農作業をする方が多かった頃にはとても重要な季節だったのです。
なぜならこの頃に穀物の種をまくようにしていたからです。ちょうど梅雨時期で雨が多い頃、冬の間はのんびり休んでいた百姓たちもこの時期より忙しくなるのでした。
この「芒」という字、稲とか麦の先端のとげのような部分を指す言葉なのです。「芒種」の「種」はそのままたね、意味が分かれば覚えやすいです。

二十四節気は中国より来た習慣ですが、中国ではこの時期に農作業習俗のイベントがあったり果樹の接ぎ木をしたりしているようです。農作業に関わる方にとってはさまざまな節目となる時ですね。
目次
芒種とはいつの日のこと?2025年は?
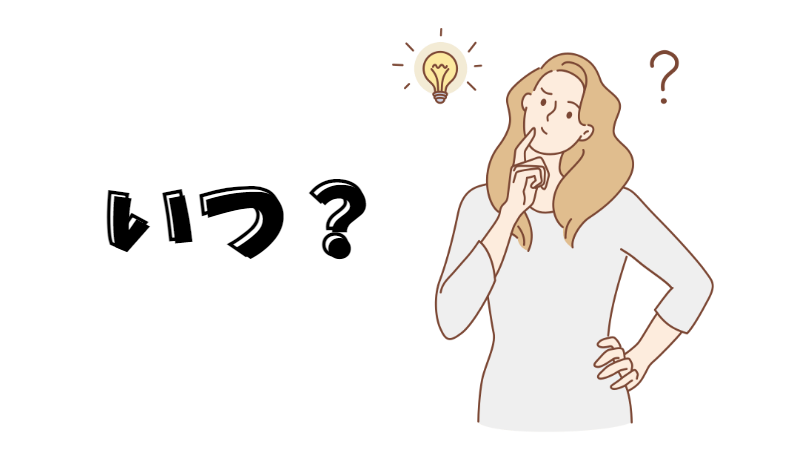
芒種の日付の例
例として2017年から2024年までの芒種は、以下のように日付が決まっています。
| 西暦 | 芒種 |
|---|---|
| 2017年 | 6月5日 |
| 2018年 | 6月6日 |
| 2019年 | 6月6日 |
| 2020年 | 6月5日 |
| 2021年 | 6月5日 |
| 2022年 | 6月6日 |
| 2023年 | 6月6日 |
| 2024年 | 6月5日 |
2025年の芒種の日付

年によって6月5日だったり、6月6日だったりと、旧暦はややこしいですね・・。
芒種の意味由来は?五月雨や五月晴れについても紹介

芒種っていつ?という疑問が解決したら、次の疑問が「春分や秋分は聞いたことがあるけれど、芒種とか聞いたことのない名前たちって一体なんなんなの?」ということかと思います。それらにもひとつひとつ意味があるのです。
芒種とは季節をあらわす旧暦の名称
毎年6月5日頃のことを旧暦で芒種と呼びます。
芒種は暦のうえでは「夏」にあたる季節の名称で、芒種の前は「小満(しょうまん)」、小満があけて芒種をすぎると6月21日頃からは「夏至(げし)」の季節がはじまります。芒種は、1年でもっとも昼間が長い夏至の一つ前の季節というわけです。
芒種の季節と由来
芒とは稲や麦などの実の殻にある毛のことで、芒の付いた実は「もみ」のこと。麦を収穫し、畑に穀物を植え付ける時期を意味しているのです。

この時期は梅雨入り前で、雨が降ることが多くなります。そして、農家では種まき・田植えの開始期にはいり、準備などで多忙を極める時期です。
「五月雨」・「五月晴れ」は芒種の時期の言葉?
「五月雨(さみだれ)」とは、梅雨入りの前から梅雨に降る長い雨のことで、芒種の時期の降り続く雨のことを指します。
「五月晴れ(さつきばれ)」とは、芒種の時期に、曇天の中少しみえた青空のことを意味していました。

しかし、明治3年の改暦で新暦が5月となり、小満の良い気候が続く季節をあらわすようになったため、「五月晴れ」は雲ひとつ無い晴天を意味するようになりました。
「五月雨」や「五月晴れ」については別記事で紹介していますので興味があれば合わせてご覧ください。
「芒種の候」はいつからいつまで?
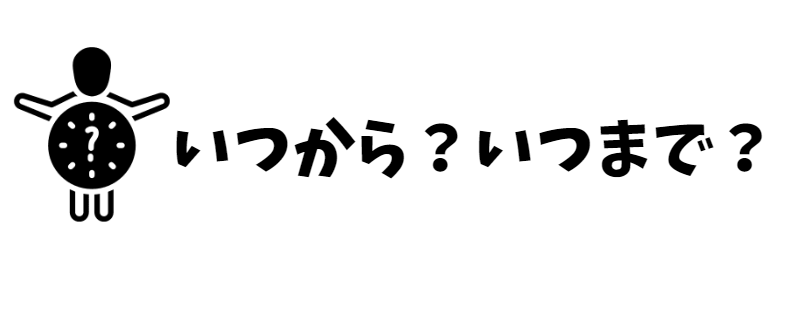
芒種の候は芒種が6月5日の年を例にすると、6月5日から6月20日まで(夏至の前日まで)をを意味しています。
お手紙の時候の挨拶で「芒種の候」を使えるのは、その期間中です。
芒種の七十二候は?

芒種の七十二候は以下のようになっています。
| 初候 | 螳螂生(かまきりしょうず) | 螳螂が生まれ出る |
|---|---|---|
| 次候 | 腐草為蛍(くされたるくさほたるとなる) | 腐った草が蒸れ蛍になる |
| 末候 | 梅子黄(うめのみきばむ) | 梅の実が黄ばんで熟す |
カマキリや蛍が現れ始めたり、梅の実が黄ばみ始めたり、蒸し暑くなってきている様子が表現されています。

今はなかなかお目にかかれないような情景の描写ですが、じめじめしている様子が伝わってきますね。
まとめ
芒種について、理解できたでしょうか。理解するのにここまで様々な周辺知識が必要な言葉も、日本の歴史ならではですね。旧暦と新暦は本当にややこしいですよね。
日常生活で使うことはまずないですし覚えていなくも困る場面は滅多にないとは思いますが、芒種の時期になったら少しだけ、昔の人が感じていた感覚を、自分も探してみるのも悪くないかもしれません。