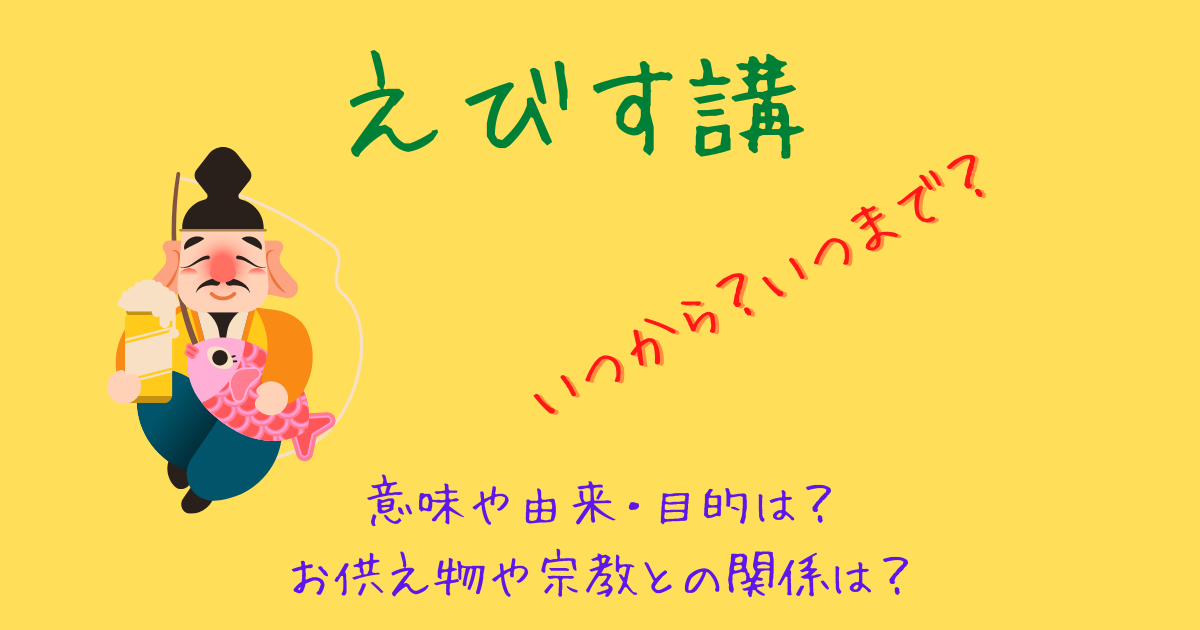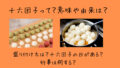いつ開催されているのかなど、詳しくみていきます。日本の宗教観もお分かりいただけるはずです。
えびす講はいつから?いつまで?地域によって違う?
1月10日から20日というところもあれば10月20日というところも、11月20日ということもあります。
中には10月20日と1月20日、年に2回といったところまであったりします。
元々は旧暦の10月・すなわち神無月の行事でした。そのため全国的に10月11月開催のところが多いです。
地域によって旧暦のままであったり新暦に直して・平日では無くその前後である土日を開催日としてと変えているのです。
1月開催の地域は「十日えびす」との名で1月10日を中心にあります。歳の市と結びつけることで新暦である12月20日に、4月におこなわれるのは1月が年の始まりなら4月は学業を学ぶ上での始まりの月だからこそでしょうか。
自分の住む地域のえびす講がいつからいつまであるのか、なぜその日の開催となったかなど調べるとおもしろいかもしれません。

開催の日程は異なるものの、全国的にえびす講がおこなわれているのは確かです。それぞれの地域で名前も違ったりしますので、地域名+えびす講でチェックしてみましょう!
えびす講の意味や由来・目的は?
実はこの神様、神無月・つまり10月に日本全国の神様たちが島根県の出雲大社に集まるときに彼だけは留守番役として地域に残る役割も持っているのです。
つまり神のいない月だけれどもえびす様だけはいらっしゃるということ、そんなえびす様を慰めたいとのことで始まったお祭りなのです。
留守番役だからといって決して格下の神様というわけではありません。商売繁盛に五穀豊穣・更には豊漁とあらゆる利益をもたらしてくれる、守備範囲の広い神様です。
せっかく残っていらっしゃるすばらしい神様、おまつりすることで一年間商売も農業も漁業も上手くいき幸せに暮らせますように、そういった願いも込められているわけです。
恵比寿神社で毎年10月にあるべったら市も実はえびす講が正式名称、べったら市というのは通称なのです。さまざまに名を変え、開催日も変えながらも全国で大昔よりおこなわれています。

自分のところでは聞いたこともないという方、毎年行っているあの行事もえびす講かもしれませんよ!
えびす講のお供え物は?
ぜひえびす様にお供え物をして感謝をお伝えすることです。 そのためにどうすれば良いか、食べ物・縁起物などを神棚にお供えするのです。
お供えの食べ物は鯛?
生きた鮒をお供えしているといった地域もありお供え物の種類も各地バラバラ、その地域のお年寄りなどに聞くのが一番です。
えびす講をおこなう神社にお参りすると、お札をいただいたり熊手や福笹を手に入れたりもするでしょう。
これらも持って帰ってすぐ捨ててしまってはモッタイナイ、縁起物ということで神棚にお供えしましょう。
幸運も金運もかき集めてくれるという意味で熊手があるのです。風にも雪にも負けることなくまっすぐ伸びていく笹には、商売も同じようにうまくいってほしいとの願いが込められているのです。
供える場所は?神棚?玄関や床の間も?
恵比須様の持つ釣り竿との見立てもあり、神棚なんて無いというお宅も多いですが、玄関や床の間にで良いのでざひお供えしてみてください。
えびす講と宗教の関係は?
10月には神様がいないから神無月、その考え方も立派に宗教です。
そして不在となる島根県以外の土地で留守を守ってくださるありがたい神様、そんなえびす様に感謝をしつつ商売繁盛や五穀豊穣といった御利益をお願いするえびす講も、宗教から生まれたものなのです。
ちなみに、えびす講という行事名につけられた「講」という言葉、それそのものも宗教行事をおこなう結社を指す言葉です。
えびす様に大黒天・福禄寿に毘沙門天・布袋様・寿老人・弁財天、と七福神すべてを言えるかどうかはともかくある程度は日本人皆がなじみを持っているはずです。
これらの神様はそれぞれにヒンドゥー教に仏教・道教・神道とさまざまな宗教から生まれました。ちなみにえびす様はというと日本土着信仰の神様です。これらが七福神という名でセットとなり同じ船(宝船)に乗っている姿に日本らしさがあります。

宗教行事だからと敬遠する必要なし、一行事として楽しむことです。
まとめ
神無月というと神様がいない月と習ったでしょうが、実はえびす様は残り我々を見守っていてくださっているのです。
そんな神様をお慰みしようという素敵な行事であるえびす講、ぜひお供えしたり神社にお参りに行ってみることをおすすめします。